移動式クレーン構造規格
第一章 構造部分等(第一条−第十六条) |
移動式クレーン構造規格
目次
第一節 材料
(材料)
第一条 移動式クレーン(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第四
号に掲げる移動式クレーン及び同令第十三条第三項第十五号に掲げる移動式クレーンをいう。以下同じ。)
の構造部分(移動式クレーンのうち、運転室、囲い、覆いその他移動式クレーンの荷をつり上げるため
の支持部分以外の部分、機械部分及びワイヤロープを除いた部分をいう。以下同じ。)の材料は、次に
掲げる日本産業規格に適合した鋼材又はこれらと同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材でな
ければならない。ただし、厚生労働省労働基準局長が認めた場合には、この限りでない。
一 日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇
二 日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)
三 日本産業規格G三一一四(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)
四 日本産業規格G三一二八(溶接構造用高降伏点鋼板)
五 日本産業規格G三一三六(建築構造用圧延鋼材)
六 日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇、STK四九〇又はSTK
五四〇
七 日本産業規格G三四四五(機械構造用炭素鋼鋼管)に定める一三種、一八種、一九種又は二〇種
八 日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)
(鋼材に係る計算に使用する定数)
第二条 前条本文の鋼材に係る計算に使用する定数は、次の表の上欄に掲げる定数の種類に応じて、それ
ぞれ同表の下欄に掲げる値とする。(表)
第二節 基準等
第一款 構造部分の基準
(構造部分の基準)
第二条の二 第一条本文の鋼材により構成される移動式クレーンの構造部分(以下「構造部分」という。)
については、次款に規定する許容応力設計法の基準又は第三款に規定する限界状態設計法の基準に適合
するものでなければならない。
第二款 許容応力設計法
第一目 許容応力の値
(鋼材に係る許容応力の値)
第三条 第一条本文の鋼材に係る許容応力設計法の計算に使用する許容引張応力の値、許容圧縮応力の
値、許容曲げ応力の値、許容せん断応力の値及び許容支え圧応力の値は、それぞれ次の式により計算
して得た値とする。
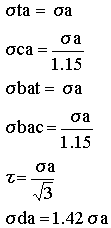
これらの式において、 σa、 σta、σca、 σbat、 σbac、τ及び σdaは、それぞれ
次の値を表すものとする。
σa鋼材に係る次に掲げる値のうちいずれか小さい値
イ 降伏点又は耐力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)の値を一・五で除して得た値
ロ 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)の値を一・八で除して得た値
σta 許容引張応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
σca 許容圧縮応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
σbat 引張応力の生ずる側における許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
σbac 圧縮応力の生ずる側における許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
τ 許容せん断応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
σda 許容支え圧応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
2 第一条本文の鋼材に係る許容応力設計法の計算に使用する許容座屈応力の値は、次の式により計算し
て得た値とする。
λ<20の場合
σk=σca
20≦λ≦200の場合
これらの式において、λ、 σ、σca、及びωは、それぞれ次の値を表すものとする。
λ 有効細長比
σk 許容座屈応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
σca 許容圧縮応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
ω 座屈係数(別表に定める座屈係数又は厚生労働省労働基準局長が認めた計算の方法により計算し
て得た値をいう。)
(溶接部に係る許容応力の値)
第四条 構造部分の溶接部に係る許容応力設計法の計算に使用する許容応力(許容支え圧応力及び許容
座屈応力を除く。)の値は、前条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するそれぞれの値(溶接加工
の方法がすみ肉溶接である場合には、許容せん断応力の値)に、次の表の上欄に掲げる溶接加工の方法
及び同表の中欄に掲げる鋼材の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とする。
(表)
2 前項の規定にかかわらず、放射線試験を行う場合において、構造部分の溶接部(溶接加工の方法が突
合溶接である場合に限る。)が次に掲げるところに該当するときは、当該溶接部に係る許容応力設計法
の計算に使用する許容応力(許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力に限る。)の値は、前条第
一項に規定する値とすることができる。
一 日本産業規格Z三一〇四(鋼溶接継手の放射線透過試験方法)(以下この条において「規格」とい
う。)に規定する第三種のきずがないこと。
二 規格に規定する第一種及び第四種のきず又は第二種のきずのいずれかがある場合には、当該きずに
係る規格に規定するきず点数又はきず長さがそれぞれ規格に規定する第一種及び第四種の二類の許容
限度を表す値又は第二種の二類の許容限度を表す値以下であること。
三 規格に規定する第一種及び第四種のきず並びに第二種のきずが混在する場合には、当該きずに係る
規格に規定するきず点数及びきず長さがそれぞれ規格に規定する第一種及び第四種の二類の許容限度
を表す値及び第二種の二類の許容限度を表す値の二分の一以下であること。
3 前項の放射線試験は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 規格に定めるところに従い構造部分の溶接部の全長の二十パーセント以上の長さについて行うこと。
二 構造部分の溶接部は、その余盛りが母材の表面と同一の面まで削られていること。ただし、余盛り
の中央における高さが、次の表の上欄に掲げる母材の厚さに応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる高
さ以下である場合には、この限りでない。(表)
(許容応力の値の特例)
第五条 第一条ただし書の規定により厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料及び当該材料
により構成される構造部分の溶接部に係る許容応力設計法の計算に使用する許容応力の値は、当該材料
の化学成分及び機械的性質を考慮して厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。
(許容応力の値の割増し)
第六条 第三条及び第四条に規定する許容応力の値及び前条の規定により厚生労働省労働基準局長が定め
る許容応力の値は、第十条第一項第二号の荷重の組合せによる計算においては、十五パーセントを限度
として割り増した値とすることができる。
第二目 荷重
(計算に使用する荷重の種類)
第七条 構造部分にかかる荷重のうち許容応力設計法の計算に使用する荷重は、次に掲げるとおりとする。
一 垂直動荷重
二 垂直静荷重
三 水平動荷重
四 風荷重
(水平動荷重)
第八条 前条第三号の水平動荷重の値は、移動式クレーンの水平に移動する部分の質量に重力加速度の値
の五パーセントに相当する値を乗じて得た値に相当する荷重及び定格荷重に重力加速度の値の五パーセ
ントに相当する値を乗じて得た値に相当する荷重が同一の水平方向に同時に作用するものとして計算し
て得た値とする。
(風荷重)
第九条 第七条第四号の風荷重の値は、次の式により計算して得た値とする。ただし、厚生労働省労働基
準局長が認めた場合には、この限りでない。
W=qCA
この式において、W、q、C及びAは、それぞれ次の値を表すものとする。
W 風荷重(単位 ニュートン)
q 速度圧(単位 ニュートン毎平方メートル)
C 風力係数
A 受圧面積(単位 平方メートル)
2 前項の速度圧の値は、次の式により計算して得た値とする。

この式において、q及びhは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 速度圧(単位 ニュートン毎平方メートル)
h 移動式クレーンの風を受ける面の地上(浮きクレーンにあっては、水面)からの高さ(単位 メ
ートル)(高さが十六メートル未満の場合には、十六)
3 第一項の風力係数は、移動式クレーンの風を受ける面に関して風洞試験を行って得た値又は次の表の
上欄に掲げる移動式クレーンの風を受ける面の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。(表)
4 第一項の受圧面積は、移動式クレーンの風を受ける面の風の方向に直角な面に対する投影面積(以下
この項において「投影面積」という。)とする。この場合において、移動式クレーンの風を受ける面が
風の方向に対して二面以上重なっているときは、風の方向に対して第一の面の投影面積に、風の方向に
対して第二以降の面(以下この項において「第二以降の面」という。)のうち風の方向に対して前方に
ある面と重なっている部分の投影面積に次の図に示す低減率を乗じて得た面積及び第二以降の面のうち
風の方向に対して前方にある面と重なっていない部分の投影面積を加えた面積とする。(図)
備考 この図において、b、h、ψ及びηは、それぞれ次の値を表すものとする。
b 相対する移動式クレーンの風を受ける面に係るけたの間隔
h 相対する移動式クレーンの風を受ける面に係るけたのうち風の方向に対して前方にあるけたの高さ
ψ 相対する移動式クレーンの風を受ける面に係るけたのうち風の方向に対して前方にあるけたの移動式
クレーンの風を受ける面に係る充実率(平面トラスにより構成される面については前項の表の備考にお
いて規定する W1とし、平板により構成される面及び円筒の面については1とする。)
η 低減率
第三目 強度
(強度計算に係る荷重の組合せ)
第十条 許容応力設計法を用いる場合にあっては、構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の値は、
次に掲げる荷重の組合せによる計算において、それぞれ第一目に規定する許容応力の値を超えてはな
らない。
一 動荷重係数を乗じた垂直動荷重及び静荷重係数を乗じた垂直静荷重の組合せ
二 動荷重係数を乗じた垂直動荷重、静荷重係数を乗じた垂直静荷重、水平動荷重及び風荷重の組合せ
2 前項の動荷重係数及び静荷重係数は、それぞれ、一・二五及び一・一とする。
3 第一項に規定する応力の値は、同項各号に掲げる荷重の組合せにおいて、当該構造部分の強度に関し
最も不利となる場合におけるそれぞれの荷重によって計算するものとする。
第三款 限界状態設計法
第一目 設計限界応力の値
(鋼材に係る設計限界応力の値)
第十条の二 第一条本文の鋼材に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界垂直応力の値、設計限
界せん断応力の値及び設計限界支え圧応力の値は、それぞれ次の式により計算して得た値とする。
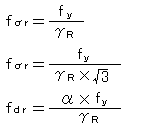
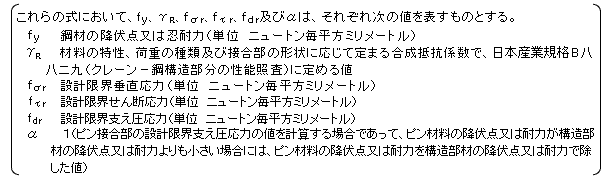 2 第一条本文の鋼材に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界座屈応力の値は、次の式により
計算して得た値とする。
2 第一条本文の鋼材に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界座屈応力の値は、次の式により
計算して得た値とする。
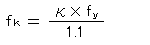
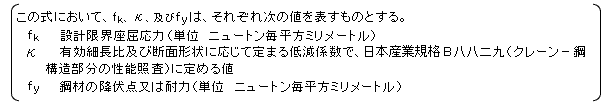 (溶接部に係る設計限界応力の値)
第十条の三 構造部分の溶接部に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力(設計限界支え圧応
力及び設計限界座屈応力を除く。)の値は、前条第一項の規定にかかわらず、次の式により計算して
得た値とする。
(溶接部に係る設計限界応力の値)
第十条の三 構造部分の溶接部に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力(設計限界支え圧応
力及び設計限界座屈応力を除く。)の値は、前条第一項の規定にかかわらず、次の式により計算して
得た値とする。
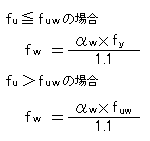
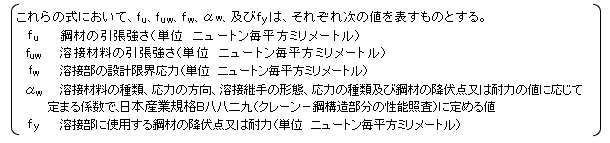 (設計限界応力の値の特例)
第十条の四 第五条の規定は、限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力の値について準用する。
第二目 荷重
(計算に使用する荷重の種類)
第十条の五 構造部分にかかる荷重のうち限界状態設計法の計算に使用する荷重は、次に掲げるとおり
とする。
一 次に掲げる定常荷重
イ 移動式クレーンの質量による荷重
ロ 定格総荷重
ハ 平たんでない場所の走行による荷重
ニ 駆動による荷重
二 非定常荷重のうち作業中の風荷重
三 次に掲げる特殊荷重
イ 地上に置かれた荷のつり上げによる荷重
ロ 休止時の風荷重
ハ 試験荷重
ニ 非常停止による荷重
(風荷重)
第十条の六 第九条の規定は、前条第二号の非定常荷重のうち作業中の風荷重について準用する。この場
合において、第九条第一項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは、「第十条の五第二号の非定常荷重
のうち作業中の風荷重」と読み替えるものとする。
2 第九条の規定は、前条第三号ロの休止時の風荷重について準用する。この場合において、第九条第一
項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは「第十条の五第三号ロの休止時の風荷重」と、同条第二項中
「q=834√h」とあるのは「q=9804√h」と読み替えるものとする。
(試験荷重)
第十条の七 第十条の五第三号ハの試験荷重の値は、定格総荷重に一・二五を乗じた値とする。
第三目 強度
(強度計算に係る荷重の組合せ)
第十条の八 限界状態設計法を用いる場合にあっては、構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の
値は、次に掲げる荷重又は荷重の組合せによる計算において、それぞれ第一目に規定する設計限界応力
の値を超えてはならない。
一 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重の組合せ
二 平たんでない場所の走行による荷重
三 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重並びに作業中の風荷重の組合せ
四 平たんでない場所の走行による荷重及び作業中の風荷重の組合せ
五 移動式クレーンの質量による荷重及び地上に置かれた荷のつり上げによる荷重の組合せ
六 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び休止時の風荷重の組合せ
七 移動式クレーンの質量による荷重、駆動による荷重、作業中の風荷重及び試験荷重の組合せ
八 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び非常停止による荷重の組合せ
2 前項各号の荷重又は荷重の組合せによる計算においては、それぞれの荷重に日本産業規格B八八三三
−二(クレーン−荷重及び荷重の組合せに関する設計原則−第二部:移動式クレーン)に定める部分荷
重係数及び動的影響係数を乗じるものとする。
3 第一項に規定する応力の値は、同項各号に掲げる荷重の組合せにおいて、当該構造部分の強度に関し
最も不利となる場合におけるそれぞれの荷重によって計算するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、移動式クレーンの設計の基準とする負荷条件に応じて、負荷されること
が想定されない荷重又は荷重の組合せについては、省略することができる。
第三節 安全性等
(疲れ強さに対する安全性)
第十一条 許容応力設計法を用いる場合にあっては、構造部分は、疲れ強さに対する安全性が確認され
たものでなければならない。
(剛性の保持)
第十二条 構造部分は、壁面座屈、著しい変形等が生じないように剛性が保持されているものでなければ
ならない。
(後方安定度)
第十三条 移動式クレーン(クローラクレーン及び浮きクレーンを除く。)は、次の各号に掲げるジブの
長手方向の中心線を含む鉛直面と当該移動式クレーンの走行方向との状態に応じて、当該ジブが向けら
れている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値がそれぞれ当該各号に定める値以上である後
方安定度を有するものでなければならない。
一 直角である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値
二 平行である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値に平均輪距を軸距で除して得た値を乗じて得た値
2 クローラクレーンは、ジブが向けられている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値が、当
該クローラクレーンの質量に重力加速度の値の十五パーセントに相当する値を乗じて得た値以上である
後方安定度を有するものでなければならない。
3 前二項に規定する後方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 後方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの後方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 荷をつっていない状態にあること。
三 水平かつ堅固な面の上にあること。
四 アウトリガーを有する移動式クレーンにあっては、当該アウトリガーを使用しない状態にあること。
ただし、自動的にアウトリガーの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角
度又はジブの傾斜角を制限する安全装置を備えている移動式クレーンにあっては、当該アウトリガー
を使用した状態とすることができる。
五 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出さない状態にある
こと。ただし、クローラを最大限に張り出していない状態で定格荷重を有しないクローラクレーン及
び自動的にクローラの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角度又はジブ
の傾斜角を制限する安全装置を備えているクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出した
状態とすることができる。
(前方安定度)
第十四条 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)は、安定限界総荷重の値が、定格総荷重に一・二
五を乗じた値にジブの質量のうち先端部等価質量に〇・一を乗じた値を加えた値以上である前方安定度
を有するものでなければならない。
2 前項に規定する前方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 前方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの前方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 水平かつ堅固な面の上にあること。
(浮きクレーンの安定度)
第十五条 浮きクレーンは、静穏な水面で定格荷重に相当する荷重をつった状態において、転倒端におけ
る乾舷(げん)(上甲板から水面までの垂直距離をいう。)が〇・三メートル以上となるものでなければ
ならない。
(左右の安定度)
第十六条 移動式クレーン(クローラクレーンを除く。)は、次の状態において、水平かつ堅固な面の上
で三十度まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものでなければならない。
一 無負荷状態(燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し、かつ、運転に必要な設備、装置等を取り付
けた状態をいう。以下同じ。)にあること。
二 ジブが走行時の姿勢として定められた状態にあること。
2 前項に規定する左右の安定度は、計算によって算定することができる。
(設計限界応力の値の特例)
第十条の四 第五条の規定は、限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力の値について準用する。
第二目 荷重
(計算に使用する荷重の種類)
第十条の五 構造部分にかかる荷重のうち限界状態設計法の計算に使用する荷重は、次に掲げるとおり
とする。
一 次に掲げる定常荷重
イ 移動式クレーンの質量による荷重
ロ 定格総荷重
ハ 平たんでない場所の走行による荷重
ニ 駆動による荷重
二 非定常荷重のうち作業中の風荷重
三 次に掲げる特殊荷重
イ 地上に置かれた荷のつり上げによる荷重
ロ 休止時の風荷重
ハ 試験荷重
ニ 非常停止による荷重
(風荷重)
第十条の六 第九条の規定は、前条第二号の非定常荷重のうち作業中の風荷重について準用する。この場
合において、第九条第一項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは、「第十条の五第二号の非定常荷重
のうち作業中の風荷重」と読み替えるものとする。
2 第九条の規定は、前条第三号ロの休止時の風荷重について準用する。この場合において、第九条第一
項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは「第十条の五第三号ロの休止時の風荷重」と、同条第二項中
「q=834√h」とあるのは「q=9804√h」と読み替えるものとする。
(試験荷重)
第十条の七 第十条の五第三号ハの試験荷重の値は、定格総荷重に一・二五を乗じた値とする。
第三目 強度
(強度計算に係る荷重の組合せ)
第十条の八 限界状態設計法を用いる場合にあっては、構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の
値は、次に掲げる荷重又は荷重の組合せによる計算において、それぞれ第一目に規定する設計限界応力
の値を超えてはならない。
一 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重の組合せ
二 平たんでない場所の走行による荷重
三 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重並びに作業中の風荷重の組合せ
四 平たんでない場所の走行による荷重及び作業中の風荷重の組合せ
五 移動式クレーンの質量による荷重及び地上に置かれた荷のつり上げによる荷重の組合せ
六 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び休止時の風荷重の組合せ
七 移動式クレーンの質量による荷重、駆動による荷重、作業中の風荷重及び試験荷重の組合せ
八 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び非常停止による荷重の組合せ
2 前項各号の荷重又は荷重の組合せによる計算においては、それぞれの荷重に日本産業規格B八八三三
−二(クレーン−荷重及び荷重の組合せに関する設計原則−第二部:移動式クレーン)に定める部分荷
重係数及び動的影響係数を乗じるものとする。
3 第一項に規定する応力の値は、同項各号に掲げる荷重の組合せにおいて、当該構造部分の強度に関し
最も不利となる場合におけるそれぞれの荷重によって計算するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、移動式クレーンの設計の基準とする負荷条件に応じて、負荷されること
が想定されない荷重又は荷重の組合せについては、省略することができる。
第三節 安全性等
(疲れ強さに対する安全性)
第十一条 許容応力設計法を用いる場合にあっては、構造部分は、疲れ強さに対する安全性が確認され
たものでなければならない。
(剛性の保持)
第十二条 構造部分は、壁面座屈、著しい変形等が生じないように剛性が保持されているものでなければ
ならない。
(後方安定度)
第十三条 移動式クレーン(クローラクレーン及び浮きクレーンを除く。)は、次の各号に掲げるジブの
長手方向の中心線を含む鉛直面と当該移動式クレーンの走行方向との状態に応じて、当該ジブが向けら
れている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値がそれぞれ当該各号に定める値以上である後
方安定度を有するものでなければならない。
一 直角である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値
二 平行である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値に平均輪距を軸距で除して得た値を乗じて得た値
2 クローラクレーンは、ジブが向けられている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値が、当
該クローラクレーンの質量に重力加速度の値の十五パーセントに相当する値を乗じて得た値以上である
後方安定度を有するものでなければならない。
3 前二項に規定する後方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 後方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの後方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 荷をつっていない状態にあること。
三 水平かつ堅固な面の上にあること。
四 アウトリガーを有する移動式クレーンにあっては、当該アウトリガーを使用しない状態にあること。
ただし、自動的にアウトリガーの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角
度又はジブの傾斜角を制限する安全装置を備えている移動式クレーンにあっては、当該アウトリガー
を使用した状態とすることができる。
五 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出さない状態にある
こと。ただし、クローラを最大限に張り出していない状態で定格荷重を有しないクローラクレーン及
び自動的にクローラの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角度又はジブ
の傾斜角を制限する安全装置を備えているクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出した
状態とすることができる。
(前方安定度)
第十四条 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)は、安定限界総荷重の値が、定格総荷重に一・二
五を乗じた値にジブの質量のうち先端部等価質量に〇・一を乗じた値を加えた値以上である前方安定度
を有するものでなければならない。
2 前項に規定する前方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 前方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの前方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 水平かつ堅固な面の上にあること。
(浮きクレーンの安定度)
第十五条 浮きクレーンは、静穏な水面で定格荷重に相当する荷重をつった状態において、転倒端におけ
る乾舷(げん)(上甲板から水面までの垂直距離をいう。)が〇・三メートル以上となるものでなければ
ならない。
(左右の安定度)
第十六条 移動式クレーン(クローラクレーンを除く。)は、次の状態において、水平かつ堅固な面の上
で三十度まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものでなければならない。
一 無負荷状態(燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し、かつ、運転に必要な設備、装置等を取り付
けた状態をいう。以下同じ。)にあること。
二 ジブが走行時の姿勢として定められた状態にあること。
2 前項に規定する左右の安定度は、計算によって算定することができる。
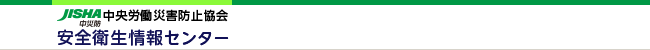
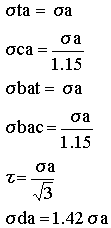
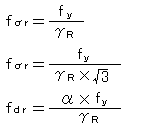
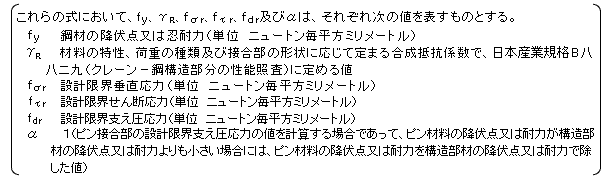 2 第一条本文の鋼材に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界座屈応力の値は、次の式により
計算して得た値とする。
2 第一条本文の鋼材に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界座屈応力の値は、次の式により
計算して得た値とする。
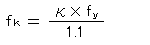
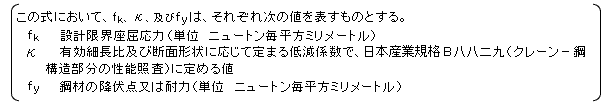 (溶接部に係る設計限界応力の値)
第十条の三 構造部分の溶接部に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力(設計限界支え圧応
力及び設計限界座屈応力を除く。)の値は、前条第一項の規定にかかわらず、次の式により計算して
得た値とする。
(溶接部に係る設計限界応力の値)
第十条の三 構造部分の溶接部に係る限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力(設計限界支え圧応
力及び設計限界座屈応力を除く。)の値は、前条第一項の規定にかかわらず、次の式により計算して
得た値とする。
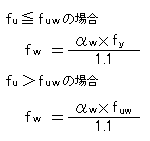
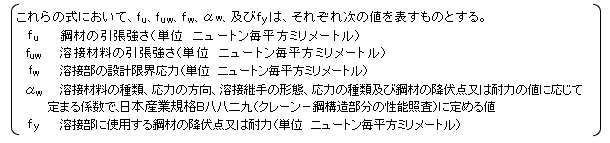 (設計限界応力の値の特例)
第十条の四 第五条の規定は、限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力の値について準用する。
第二目 荷重
(計算に使用する荷重の種類)
第十条の五 構造部分にかかる荷重のうち限界状態設計法の計算に使用する荷重は、次に掲げるとおり
とする。
一 次に掲げる定常荷重
イ 移動式クレーンの質量による荷重
ロ 定格総荷重
ハ 平たんでない場所の走行による荷重
ニ 駆動による荷重
二 非定常荷重のうち作業中の風荷重
三 次に掲げる特殊荷重
イ 地上に置かれた荷のつり上げによる荷重
ロ 休止時の風荷重
ハ 試験荷重
ニ 非常停止による荷重
(風荷重)
第十条の六 第九条の規定は、前条第二号の非定常荷重のうち作業中の風荷重について準用する。この場
合において、第九条第一項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは、「第十条の五第二号の非定常荷重
のうち作業中の風荷重」と読み替えるものとする。
2 第九条の規定は、前条第三号ロの休止時の風荷重について準用する。この場合において、第九条第一
項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは「第十条の五第三号ロの休止時の風荷重」と、同条第二項中
「q=834√h」とあるのは「q=9804√h」と読み替えるものとする。
(試験荷重)
第十条の七 第十条の五第三号ハの試験荷重の値は、定格総荷重に一・二五を乗じた値とする。
第三目 強度
(強度計算に係る荷重の組合せ)
第十条の八 限界状態設計法を用いる場合にあっては、構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の
値は、次に掲げる荷重又は荷重の組合せによる計算において、それぞれ第一目に規定する設計限界応力
の値を超えてはならない。
一 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重の組合せ
二 平たんでない場所の走行による荷重
三 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重並びに作業中の風荷重の組合せ
四 平たんでない場所の走行による荷重及び作業中の風荷重の組合せ
五 移動式クレーンの質量による荷重及び地上に置かれた荷のつり上げによる荷重の組合せ
六 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び休止時の風荷重の組合せ
七 移動式クレーンの質量による荷重、駆動による荷重、作業中の風荷重及び試験荷重の組合せ
八 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び非常停止による荷重の組合せ
2 前項各号の荷重又は荷重の組合せによる計算においては、それぞれの荷重に日本産業規格B八八三三
−二(クレーン−荷重及び荷重の組合せに関する設計原則−第二部:移動式クレーン)に定める部分荷
重係数及び動的影響係数を乗じるものとする。
3 第一項に規定する応力の値は、同項各号に掲げる荷重の組合せにおいて、当該構造部分の強度に関し
最も不利となる場合におけるそれぞれの荷重によって計算するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、移動式クレーンの設計の基準とする負荷条件に応じて、負荷されること
が想定されない荷重又は荷重の組合せについては、省略することができる。
第三節 安全性等
(疲れ強さに対する安全性)
第十一条 許容応力設計法を用いる場合にあっては、構造部分は、疲れ強さに対する安全性が確認され
たものでなければならない。
(剛性の保持)
第十二条 構造部分は、壁面座屈、著しい変形等が生じないように剛性が保持されているものでなければ
ならない。
(後方安定度)
第十三条 移動式クレーン(クローラクレーン及び浮きクレーンを除く。)は、次の各号に掲げるジブの
長手方向の中心線を含む鉛直面と当該移動式クレーンの走行方向との状態に応じて、当該ジブが向けら
れている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値がそれぞれ当該各号に定める値以上である後
方安定度を有するものでなければならない。
一 直角である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値
二 平行である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値に平均輪距を軸距で除して得た値を乗じて得た値
2 クローラクレーンは、ジブが向けられている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値が、当
該クローラクレーンの質量に重力加速度の値の十五パーセントに相当する値を乗じて得た値以上である
後方安定度を有するものでなければならない。
3 前二項に規定する後方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 後方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの後方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 荷をつっていない状態にあること。
三 水平かつ堅固な面の上にあること。
四 アウトリガーを有する移動式クレーンにあっては、当該アウトリガーを使用しない状態にあること。
ただし、自動的にアウトリガーの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角
度又はジブの傾斜角を制限する安全装置を備えている移動式クレーンにあっては、当該アウトリガー
を使用した状態とすることができる。
五 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出さない状態にある
こと。ただし、クローラを最大限に張り出していない状態で定格荷重を有しないクローラクレーン及
び自動的にクローラの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角度又はジブ
の傾斜角を制限する安全装置を備えているクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出した
状態とすることができる。
(前方安定度)
第十四条 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)は、安定限界総荷重の値が、定格総荷重に一・二
五を乗じた値にジブの質量のうち先端部等価質量に〇・一を乗じた値を加えた値以上である前方安定度
を有するものでなければならない。
2 前項に規定する前方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 前方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの前方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 水平かつ堅固な面の上にあること。
(浮きクレーンの安定度)
第十五条 浮きクレーンは、静穏な水面で定格荷重に相当する荷重をつった状態において、転倒端におけ
る乾舷(げん)(上甲板から水面までの垂直距離をいう。)が〇・三メートル以上となるものでなければ
ならない。
(左右の安定度)
第十六条 移動式クレーン(クローラクレーンを除く。)は、次の状態において、水平かつ堅固な面の上
で三十度まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものでなければならない。
一 無負荷状態(燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し、かつ、運転に必要な設備、装置等を取り付
けた状態をいう。以下同じ。)にあること。
二 ジブが走行時の姿勢として定められた状態にあること。
2 前項に規定する左右の安定度は、計算によって算定することができる。
(設計限界応力の値の特例)
第十条の四 第五条の規定は、限界状態設計法の計算に使用する設計限界応力の値について準用する。
第二目 荷重
(計算に使用する荷重の種類)
第十条の五 構造部分にかかる荷重のうち限界状態設計法の計算に使用する荷重は、次に掲げるとおり
とする。
一 次に掲げる定常荷重
イ 移動式クレーンの質量による荷重
ロ 定格総荷重
ハ 平たんでない場所の走行による荷重
ニ 駆動による荷重
二 非定常荷重のうち作業中の風荷重
三 次に掲げる特殊荷重
イ 地上に置かれた荷のつり上げによる荷重
ロ 休止時の風荷重
ハ 試験荷重
ニ 非常停止による荷重
(風荷重)
第十条の六 第九条の規定は、前条第二号の非定常荷重のうち作業中の風荷重について準用する。この場
合において、第九条第一項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは、「第十条の五第二号の非定常荷重
のうち作業中の風荷重」と読み替えるものとする。
2 第九条の規定は、前条第三号ロの休止時の風荷重について準用する。この場合において、第九条第一
項中「第七条第四号の風荷重」とあるのは「第十条の五第三号ロの休止時の風荷重」と、同条第二項中
「q=834√h」とあるのは「q=9804√h」と読み替えるものとする。
(試験荷重)
第十条の七 第十条の五第三号ハの試験荷重の値は、定格総荷重に一・二五を乗じた値とする。
第三目 強度
(強度計算に係る荷重の組合せ)
第十条の八 限界状態設計法を用いる場合にあっては、構造部分を構成する部材の断面に生ずる応力の
値は、次に掲げる荷重又は荷重の組合せによる計算において、それぞれ第一目に規定する設計限界応力
の値を超えてはならない。
一 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重の組合せ
二 平たんでない場所の走行による荷重
三 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び駆動による荷重並びに作業中の風荷重の組合せ
四 平たんでない場所の走行による荷重及び作業中の風荷重の組合せ
五 移動式クレーンの質量による荷重及び地上に置かれた荷のつり上げによる荷重の組合せ
六 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び休止時の風荷重の組合せ
七 移動式クレーンの質量による荷重、駆動による荷重、作業中の風荷重及び試験荷重の組合せ
八 移動式クレーンの質量による荷重、定格総荷重及び非常停止による荷重の組合せ
2 前項各号の荷重又は荷重の組合せによる計算においては、それぞれの荷重に日本産業規格B八八三三
−二(クレーン−荷重及び荷重の組合せに関する設計原則−第二部:移動式クレーン)に定める部分荷
重係数及び動的影響係数を乗じるものとする。
3 第一項に規定する応力の値は、同項各号に掲げる荷重の組合せにおいて、当該構造部分の強度に関し
最も不利となる場合におけるそれぞれの荷重によって計算するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、移動式クレーンの設計の基準とする負荷条件に応じて、負荷されること
が想定されない荷重又は荷重の組合せについては、省略することができる。
第三節 安全性等
(疲れ強さに対する安全性)
第十一条 許容応力設計法を用いる場合にあっては、構造部分は、疲れ強さに対する安全性が確認され
たものでなければならない。
(剛性の保持)
第十二条 構造部分は、壁面座屈、著しい変形等が生じないように剛性が保持されているものでなければ
ならない。
(後方安定度)
第十三条 移動式クレーン(クローラクレーン及び浮きクレーンを除く。)は、次の各号に掲げるジブの
長手方向の中心線を含む鉛直面と当該移動式クレーンの走行方向との状態に応じて、当該ジブが向けら
れている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値がそれぞれ当該各号に定める値以上である後
方安定度を有するものでなければならない。
一 直角である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値
二 平行である場合 当該移動式クレーンの質量に重力加速度を乗じて得た値の十五パーセントに相当
する値を乗じて得た値に平均輪距を軸距で除して得た値を乗じて得た値
2 クローラクレーンは、ジブが向けられている側のすべての転倒支点にかかる荷重の値の合計値が、当
該クローラクレーンの質量に重力加速度の値の十五パーセントに相当する値を乗じて得た値以上である
後方安定度を有するものでなければならない。
3 前二項に規定する後方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 後方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの後方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 荷をつっていない状態にあること。
三 水平かつ堅固な面の上にあること。
四 アウトリガーを有する移動式クレーンにあっては、当該アウトリガーを使用しない状態にあること。
ただし、自動的にアウトリガーの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角
度又はジブの傾斜角を制限する安全装置を備えている移動式クレーンにあっては、当該アウトリガー
を使用した状態とすることができる。
五 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出さない状態にある
こと。ただし、クローラを最大限に張り出していない状態で定格荷重を有しないクローラクレーン及
び自動的にクローラの張出幅を検出して、後方安定度を確保することができるよう旋回角度又はジブ
の傾斜角を制限する安全装置を備えているクローラクレーンにあっては、当該クローラを張り出した
状態とすることができる。
(前方安定度)
第十四条 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)は、安定限界総荷重の値が、定格総荷重に一・二
五を乗じた値にジブの質量のうち先端部等価質量に〇・一を乗じた値を加えた値以上である前方安定度
を有するものでなければならない。
2 前項に規定する前方安定度は、移動式クレーンが次の状態にあるものとして計算するものとする。
一 前方安定度に影響がある質量は、移動式クレーンの前方安定に関し最も不利となる状態にあること。
二 水平かつ堅固な面の上にあること。
(浮きクレーンの安定度)
第十五条 浮きクレーンは、静穏な水面で定格荷重に相当する荷重をつった状態において、転倒端におけ
る乾舷(げん)(上甲板から水面までの垂直距離をいう。)が〇・三メートル以上となるものでなければ
ならない。
(左右の安定度)
第十六条 移動式クレーン(クローラクレーンを除く。)は、次の状態において、水平かつ堅固な面の上
で三十度まで傾けても転倒しない左右の安定度を有するものでなければならない。
一 無負荷状態(燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し、かつ、運転に必要な設備、装置等を取り付
けた状態をいう。以下同じ。)にあること。
二 ジブが走行時の姿勢として定められた状態にあること。
2 前項に規定する左右の安定度は、計算によって算定することができる。