安全衛生情報センター
令和6年能登半島地震による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について
基安安発0104第2号
基安労発0104第3号
基安化発0104第2号
令和6年1月4日
建設業労働災害防止協会 専務理事
建設労務安全研究会 理事長
社団法人日本建設業連合会 専務理事
一般社団法人全国建設業協会 専務理事
一般社団法人全国中小建設業協会 専務理事
建設労務安全研究会 理事長
社団法人日本建設業連合会 専務理事
一般社団法人全国建設業協会 専務理事
一般社団法人全国中小建設業協会 専務理事

殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長
令和6年能登半島地震による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について
今般、令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、北陸地方の広い範囲の数多くの箇所において、 家屋の倒壊、土砂崩壊等が発生するなど、国民生活に甚大な被害が発生しています。 今後、道路等のインフラの復旧、がれきの処理や建築物の解体・改修工事等の災害復旧工事が本格化す ることが見込まれますが、災害復旧工事においては、地山が崩れやすくなっている可能性がある箇所での 土砂崩壊災害、がれきの処理作業や建築物の解体等作業に伴う建設機械による災害等、労働災害の発生が 懸念されます。こうしたことから、貴会におかれては、今後の労働災害防止対策のより一層の徹底を図る とともに、下記の事項を踏まえた災害復旧工事における労働災害防止対策について、貴会会員各位に対し 周知徹底を図られますようお願いします。
記
1 土砂崩壊災害防止対策 (1) 地山の掘削を伴う工事の施工に当たっては、地震の影響により地山が崩れやすくなっている可能性 があることに十分に留意の上、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第355条に基づき、作業 箇所及びその周辺の地山について、形状、地質及び地層の状態、含水及び湧水の状態等をあらかじめ 十分に調査すること。 また、今回の地震以前から着工している工事についても、必要に応じ、改めて同様の調査を行うこ と。 (2) 上記(1)の調査結果を踏まえ、作業計画を定め、又は作業計画を変更し、これに基づき作業を行う こと。 (3) 掘削の作業に当たっては、安衛則第358条に基づき点検者を指名し、作業箇所及びその周辺の地山 について、通常の場合よりも頻度を高めて点検を行うことにより、地山の異常をできるだけ早期に発 見するよう努めること。また、必要に応じ、地山の状況を監視する者を配置すること。 (4) 土砂崩壊のおそれがある場合には、安衛則第361条に基づき、あらかじめ、堅固な構造の土止め支 保工を設ける等土砂崩壊による災害を防止するための措置を講ずること。また、土止め支保工を設け る等の作業中における災害の防止にも留意すること。 (5) 平成27年6月29日付け基安安発0629第1号の別添1「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガ イドライン」に基づき、日常点検、変状時の点検を確実に行うこと。また、斜面の変状の進行を確認 した場合は、施工者、発注者等は、安全性検討関係者会議において斜面の状況に対応するためのハー ド対策等の労働災害防止のための措置を検討すること。 (6) 復旧工事のうち、地山の掘削を伴わない工事についても、斜面の近傍で工事を実施する場合には、 上記(1)から(5)までに準じ、事前調査及び点検、土砂崩壊のおそれがある場合における措置の徹底を 図ること。 (7) 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全確保については、下記4によること。 2 墜落・転落災害防止対策 木造家屋等低層住宅の屋根等の改修等工事においては、墜落防止措置がとられず、屋根の踏み抜きを 含む墜落・転落災害が発生しがちであることから、木造家屋等低層住宅の屋根等の改修等工事で作業床 を設けることが困難な場合には、要求性能墜落制止用器具等の取付設備を設置した上で、要求性能墜落 制止用器具を確実に使用させること。この際には、リーフレット「足場の設置が困難な屋根上作業での 墜落防止対策のポイント」※を参考にすること。 ※http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/140805-1.pdf 3 がれき処理作業及び損壊した建物等への立入り時における安全確保及び石綿粉じん等のばく露防止対 策 (1) 円滑な災害復旧の観点から短期間での作業が求められるが、労働災害防止のため、当日の作業内容、 安全上の注意事項等について作業開始前のミーティング等を綿密に実施すること。 (2) ヘルメットや安全靴、丈夫な手袋など適切な保護具を着用すること。特に、安全靴は、底の厚い靴、 踏み抜き防止中敷きを使用すること。 (3) 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全の確保については、下記4によること。 (4) 適切な呼吸用保護具の着用等、石綿粉じんその他の粉じんを吸入することを防止するための措置を 徹底すること。また、建築物のがれき処理作業や解体作業等の際には、事前に石綿の有無の確認等を 徹底すること。 4 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全の確保 (1) 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全を確保するために、安衛則第155条に基づき、 作業全体の計画を作成し、これに基づく作業を徹底すること。 (2) 災害復旧工事においては、特に、車両系建設機械を使用した作業と人力による作業が輻輳して行わ れることが想定されることから、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、安衛則第158条に基づき、 立入りを禁止する措置を講ずる、又は誘導者を配置してその者に車両系建設機械を誘導させることに より、車両系建設機械相互又は車両系建設機械と作業員との接触防止を徹底すること。 (3) 不安定な作業場所において車両系建設機械を使用して作業を行うこととなるため、安衛則第157条 に基づき、運行経路の路肩の崩壊防止、地盤の不同沈下の防止、必要な幅員の保持等により、車両系 建設機械の転倒防止対策の徹底を図ること。 (4) 車両系建設機械の運転の業務については、技能講習を修了した者等必要な資格を有する者に行わせ ること。 5 その他 (1) 本震の発災から当面の間は強い余震が想定されることから、工事に伴う作業中に余震が起こるなど の窮迫した危険が生じた場合における緊急連絡体制を確立するとともに、避難の方法等を労働者に十 分周知すること。また、余震による倒壊を防止するための措置について検討し、必要な対策を講じて おくこと。 (2) 倒壊のおそれのある家屋等の建築物に不用意に接近しないようにするとともに、建設機械を使用す る作業場所においては、機械との接触防止措置等を徹底すること。 3(4)のほか、粉じんを吸入するおそれのある作業については、適切な呼吸用保護具の着用等を徹底 すること。また、冬季の屋外作業においては、寒冷環境下での作業が予想されることから、暖房設備 を備えた休憩設備を設置するほか、適切な防寒具等を着用させること。 (3) 復旧工事では、多数の建設業者による作業が輻輳して行われることが想定され、また、復旧工事に 当たる建設業者も被災地域の内外から集まるため、必ずしも密接な情報共有や連携がなされないこと が懸念される。こうした状況を踏まえ、隣接する現場で異なる復旧工事が行われることによる労働災 害を防止する観点から、隣接する現場を担当する建設業者間で、事前に工事内容や作業計画について 情報の共有を行うこと。 (4) 被災地(特に住宅地)での復旧工事は、通常の建設現場のように部外者の立入りが制限されず、倒壊 した自宅で家財道具等を探す住民や瓦礫撤去や清掃といった作業を行う災害ボランティア等が作業範 囲内に立ち入る可能性がある。そのため、車両系建設機械等を用いた復旧工事において、住民や災害 ボランティアを負傷させることのないよう、監視員の配置や現場への立入りを制限する等、必要な措 置を講じること。 (5) 冬季においては積雪や路面の凍結等によって転倒災害のリスクが高まることから十分注意して作業 するとともに、必要に応じて滑りにくい靴の着用等による転倒災害防止対策に留意すること。 (添付) 関連リーフレット ・資料1 災害からの復旧工事の安全な施工について ・資料2 がれきの処理作業を行う際の注意事項〜がれき処理作業を行う皆様へ〜 ・資料3 がれきの処理作業を行う際の注意事項〜事業者の皆様へ〜
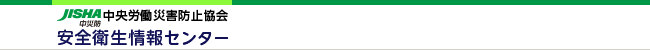

 (PDF:187KB)
(PDF:187KB)