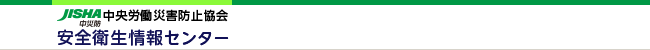
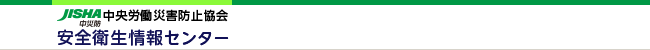
|
参考 爆発危険箇所の分類について 新構造規格第1条第15号から第17号までに定めるガス又は蒸気が爆発の危険のある濃度に達するおそれの ある箇所(以下「爆発危険箇所」という。)について、新構造規格第1条第15号から第17号までに定める 「特別危険箇所」、「第一類危険箇所」及び「第二類危険箇所」に分類する方法は、JISC60079-10(爆発 性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類)によるが、その概要は下記のとおりである。 また、分類は、可燃性物質の特性、爆発に至る過程及び電気機械器具に関する知識を持つ者が、安全、 電気、機械その他の関係技術者と適宜協議の上、実施すること。 1 放出等級の決定 ガス又は蒸気の爆発性雰囲気の生成頻度及び可能性に応じ、ガス又は蒸気の放出源(以下単に「放出 源」という。)を次のいずれかの「放出等級」に分類すること。 なお、(2)及び(3)並びに3の(2)及び(3)において、「通常運転中」とは、ガス又は蒸気の爆発性雰囲気 を生成するおそれのある設備又は機器が設計仕様の範囲内で稼動している状態をいうものであること。 (1)連続等級 連続的な放出又は高頻度若しくは長期にわたって発生すると予測できるガス又は蒸気の放出をいい、 例えば次に掲げる放出源が該当するものであること。 ア 常設の大気開放ベントをもつ固定屋根式タンク内の可燃性液体の表面 イ 油水分離器のような連続的又は長時間にわたって大気に開放されている可燃性液体の表面 (2)第一等級 通常運転中に周期的又はときどき発生すると予測できるガス又は蒸気の放出をいい、例えば次に掲 げる放出源が該当するものであること。 ア ポンプ、コンプレッサ又はバルブのシール部で、通常運転中に可燃性物質を大気中に放出するこ とが予測できる部分 イ 可燃性液体容器の排液部で、通常運転中の排液作業中に可燃性物質を大気中に放出することが予 測できる部分 ウ サンプル抽出部で、通常運転中に可燃性物質を大気中に放出することが予測できる部分 エ 放出弁、ベント及びその他の開口部で、通常運転中に可燃性物質を大気中へ放出することが予測 できる部分 (3)第二等級 通常運転中には発生せず、又は低頻度で短時間だけ発生すると予測できる放出をいい、例えば次に 掲げる放出源が該当するものであること。 ア ポンプ、コンプレッサ又はバルブのシール部で、通常運転中には可燃性物質を大気中に放出しな いと予測できる部分 イ フランジ、接続部及び配管附属品で、通常運転中には可燃性物質を大気中に放出しないと予測で きる部分 ウ サンプル抽出部で、通常運転中には可燃性物質を大気中に放出しないと予測できる部分 エ 放出弁、ベント及びその他の開口部で、通常運転中には可燃性物質を大気中に放出しないと予測 できる部分 2 換気度の決定 爆発危険箇所における換気について、次のいずれかの「換気度」に分類すること。 なお、換気度の分類方法については、JISC60079-10附属書B及び附属書Cを参照すること。 (1)高換気度 ガス又は蒸気の放出源において、その濃度を瞬時に低下させ、爆発下限界未満に抑えることができ る換気の能力 (2)中換気度 ガス又は蒸気の放出が継続する場合であっても、その濃度の上昇を抑制し、又は低減することがで きる換気の能力 (3)低換気度 ガス又は蒸気の放出が継続する場合、その濃度の上昇を抑制し、若しくは低減することができず、 又はガス若しくは蒸気の放出が停止した後も爆発性雰囲気が長時間持続することを防止できない換気 の能力 3 換気の有効度の決定 換気の有効度を次のいずれかに分類すること。 なお、有効度の分類方法については、JISC60079-10附属書B及び附属書Cを参照すること。 (1)良 連続した換気が行われている場合。なお、強制換気の場合には、換気装置が故障した場合には予備 の換気装置が自動的に稼働するよう措置をとること等が必要である。 (2)可 通常運転中に換気が行われているが、低頻度で短時間の換気の停止は許容される場合。なお、強制 換気の場合には、通常運転中には連続して換気を行うが、故障時には換気が停止する場合が含まれる。 (3)弱 良及び可のいずれでもないが、長時間にわたる換気の停止はない場合。なお、強制換気の場合には、 通常運転中において連続ではないものの換気を行う場合が含まれる。 なお、有効度を弱と分類することもできないほどの換気は,爆発危険箇所における換気としては不適切 であること。 4 爆発危険箇所の分類の手順 (1)から(3)までの手順に基づき爆発危険箇所を「特別危険箇所」、「第一類危険箇所」又は「第 二類危険箇所」に分類すること。 (1)原則として、連続等級の放出源は「特別危険箇所」を、第一等級の放出源は「第一類危険箇所」を、 第二等級の放出源は「第二類危険箇所」をそれぞれ形成するものであること。 (2)放出等級に加え、換気度及び換気の有効度に応じ、表に基づき分類すること。 (3)ガス又は蒸気の放出率(放出源の幾何学的形状、放出速度、濃度、揮発性及び温度によって算定さ れる放出源から単位時間当たりに放出されるガス又は蒸気の量をいう。)、爆発下限界、換気効果、 ガス又は蒸気の比重、気象条件等を考慮して爆発危険箇所の範囲を決定すること。 なお、JISC60079-10附属書Cに爆発危険箇所の分類の手順の例が示されていること。
| 放出 等級 |
換 気 度 | ||||||
| 高換気度 | 中換気度 | 低換気度 | |||||
| 有効度 「良」 |
有効度 「可」 |
有効度 「弱」 |
有効度 「良」 |
有効度 「可」 |
有効度 「弱」 |
有効度 「良」、「可」又は「弱」 |
|
| 連続 等級 |
非危険 箇所 |
第二類 危険箇所 |
第一類 危険箇所 |
特別危険 箇所 |
特別危険 (当該箇所と非危険箇所との間は第二類危険箇所) |
特別危険 (当該箇所と非危険箇所との間は第一類危険箇所) |
特別危険箇所 |
| 第一 等級 a) |
非危険 箇所 |
第二類 危険箇所 |
第二類 危険箇所 |
第一類 危険箇所 |
第一類 (当該箇所と非危険箇所との間は第二類危険箇所) |
第一類 (当該箇所と非危険箇所との間は第二類危険箇所) |
第一類危険箇所 (条件によっては特別危険箇所c)) |
| 第二 等級 b) |
非危険 箇所 |
非危険 箇所 |
第二類 危険箇所 |
第二類 危険箇所 |
第二類 危険箇所 |
第二類 危険箇所 |
第一類危険箇所 (条件によっては特別危険箇所c) ) |
注 a) 第一等級の放出源の付近に連続等級の放出源がある場合には、第一類危険箇所 及び第二類危険箇所を広めにとること。 b) 第二等級の放出源の付近に第一等級又は連続等級の放出源がある場合には、第 二類危険箇所を広めにとること。 c) 換気の能力が非常に低く、爆発性雰囲気が実質的に連続して存在する場合、特 別危険箇所となる。 |
|||||||