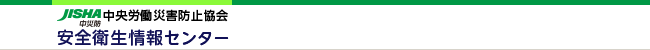
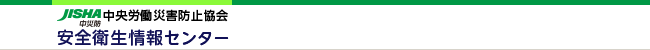
|
8.工事用設備
基本的事項 |
評価内容 |
||
| (1) 電力設備 | |||
| [1] 計画 | ・
電源計画、機器及び電線の配置計画、配線計画、回路保護及び感電防止の計画、照明設備計画等について、計画書を作成すること。 ・ 電気主任技術者及び電気取扱者を定め、その氏名を表示すること。 |
||
| [2] 受変電設備 | ・
必要電気容量の計画を適切に行い、ピーク時の容量を確保すること。 ・ 防護策、標識等の立入禁止措置を講じること。 ・ 絶縁油を使用する変圧器、開閉器及びしゃ断器は構内に設置しないこと。 |
||
| [3] 配電等 | ・
工事の進捗に応じた配線計画を行うこと。 ・ 架空電線又は電気機械器具の電路に近接する場所で作業を行う場合、電路の移設、絶縁用防具の装着等の措置を講じること。 ・ 仮設の配線又は移動電線を通路面において使用する場合は、損傷のおそれのない状態で使用すること。活線作業では、作業指揮者を指名すること。 ・ 活線作業の作業基準を作成し、関係労働者に周知すること。 ・ 移動用ケーブルは、屈曲径、許容張力及び許容電流について、定められた値の範囲内で使用し、損傷を受けるおそれのない措置を講じること。 |
||
| [4] 照明 | ・
坑内の照明回路は、途中での断線や漏電等による使用不能の場合に備えて、2回路以上とすること。 ・ 感電、電球の破損による危険を防止するためのガード等の措置を講じること。 |
||
| [5] 停電対策 | ・
停電等の事故が生じたときは、直ちに電源の切り替えができるか、又は点灯する非常灯を設けること。 ・ 直ちに関係労働者に連絡でき、かつ、安全な場所に避難できること。 ・ 回復後の再入坑時の措置を定めること。 |
||
| [6] 非常用照明 | ・
非常時において、直ちに電源の切り替えができるか、又は点灯する非常灯を設けること。 ・ 非常灯を主要機器設置箇所、坑内分岐点、休息所等坑内主要箇所に設置し、避難経路が関係労働者に分かるようにすること。 ・ 予備電源設備の定期的な保守・点検計画を作成すること。 |
||
| [7] 感電防止 | ・
高圧電源、高圧電路、変圧器等については、防護柵及び標識を設置する等の立入禁止措置を講じること。 ・ 高圧電路の固定と防護を行うこと。 ・ 架空つり下げ電灯及び手持ち形電灯(電池式、充電式を除く。)にはガードを装着すること。 ・ 交流アーク溶接機には、自動電撃防止装置を取り付けること。 ・ 坑内の電灯、電力線は支保工又は鉄管等に直接接触させず、絶縁物で遮へいすること。 ・ 絶縁用保護具、防具について定期的自主検査を行うこと。 ・ 電気機械器具で必要なものについては、感電防止用漏電しゃ断装置を設け、又はアース等の感電防止措置を講じること。 ・ 電気機械器具等について、使用前の点検及び漏えい電流の有無の検査を行うこと。 |
||
| (2) 給・配水設備 | |||
| [1] 給水設備 | ・
工事用水のほかに、消火用水、生活用水も考慮した十分な給水設備を確保すること。 ・ 工事期間中は、確実に維持、運転できるものとすること。 |
||
| [2] 排水設備 | ・
想定湧水量に工事排水を含めた総排水量に対して十分な排水能力を有する設備を計画すること。 ・ トンネルのこう配、断面及び斜坑、たて坑の存在等を十分考慮した排水設備とすること。 ・ 配水管及び排水溝は、十分な断面を有し、かつ、通行等に支障のないよう配置すること。 ・ 泥水等を排水する場合は、処理方法の計画を策定すること。 ・ 工事期間中は確実に維持、運転できるものとすること。 |
||
| [3] 使用管理 | ・ 給・排水設備の取扱い基準を定め、表示する等の方法により、関係労働者に周知すること。 | ||
| (3) 換気設備 | ・
酸素欠乏空気、有害ガス、可燃性ガス、粉じん、ディーゼル機関の排ガス及び作業者の呼気を考慮して、十分な風量の換気設備を設置すること。 ・ トンネルの規模、施工方法等を十分に検討し、最適な換気方式を選定すること。 ・ 風管は難燃性又は不燃性の製品を使用すること。 |
||
| (4) 給気設備 | ・
計画圧力、吐出量を考慮した十分な給気能力を有する設備とすること。 ・ 騒音、振動を考慮して機械の選定を行うこと。 ・ 検定に合格した圧力容器を使用すること。 ・ 安全弁の調整、圧力計の防護措置を十分に行うこと。 ・ 吐出空気の異常温度上昇を知らせるための自動警報装置を取付けること。 ・ 安全弁及び主送気管のバルブ開閉等の主要作業は取扱責任者を選任し、その者に行わせること。 |
||
| (5) 濁水処理設備 | ・
予定処理量に対して十分な能力を有する設備とすること。 ・ 排水基準に見合った能力を有する設備とすること。 ・ 排水中の懸濁物質の量(SS濃度)及び水素イオン濃度(PH)を定期的に測定すること。 ・ 排水中の油分、有害成分等の検査を定期的に行うこと。 ・ 中和剤として硫酸、塩酸等を使用する場合は、有資格者を配置すること。 |
||
| (6) 荷役設備 | ・
施工条件を考慮した適切な設備とすること。 ・ 設備の配置計画を適切に行うこと。 ・ 荷役機械等には定格荷重を表示すること。 ・ 荷役ヤードは使用計画を定めて使用すること。 ・ 荷役ヤード内への関係労働者以外の立入禁止の措置を講じること。 ・ 夜間に使用する場合は、照明設備を設けること。 ・ 荷役機械等の組立、解体時には、作業指揮者を指名すること。 |
||
| (7) ずり排出設備 | ・
施工条件を考慮した適切な設備とすること。 ・ 設備の組立、解体時には作業指揮者を指名すること。 ・ ずり排出設備内への関係労働者以外の立入禁止の措置を講じること。 |
||
| (8) 吹付けコンクリート製造設備 | ・
施工条件を考慮した適切な設備とすること。 ・ 機器周辺及び通路の照明は十分に行うこと。 ・ 墜落のおそれのある部分には覆い、囲い又は手すり等の墜落防止の措置を講じること。 ・ 保守点検を行う場合は、機械の運転を停止し、スイッチを再投入できない措置を講じること。 ・ 設備の組立、解体時には、作業指揮者を指名すること。 |
||
| (9) その他の一般機械設備 | ・
機器周辺及び通路の照明は十分に行うこと。 ・ 墜落のおそれのある部分には、覆い、囲い又は手すり等の墜落防止の措置を講じること。 ・ 取扱基準を定め、関係労働者に周知すること。 ・ 取扱責任者を指名し、表示すること。 |
||
| (10) 保守、点検 | ・
保守、点検基準を定めること。 ・ 保守、点検の責任者を定めること。 ・ 保守、点検の結果を記録し、これを保存すること。 |
||