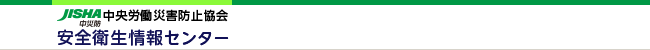
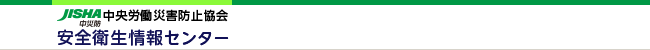
|
1.施工管理体制
基本的事項 |
評価内容 |
||||
| (1) 施工管理組織 | |||||
| [1] 現場代理人、主任技術者、監理技術者 | ・ トンネル工事に十分な経験、知識を有する現場代理人、主任技術者又は監理技術者を現場に配置すること。 | ||||
| [2] 管理組織規程 | ・ 職務内容が明確化された関係請負人を含む管理組織規程を作成し、掲示すること。 | ||||
| [3] 関係請負人の選定 | ・ 関係請負人の選定に当たっては、施工成績、安全衛生成績を考慮すること。 | ||||
| (2) 安全衛生管理 | ・ 次に掲げる者を選任すること。 | ||||
| [1] 安全衛生管理体制 | 管理者 |
対象事業場等 |
|||
| 総括安全衛生管理者 | 常時100人以上の労働者を使用する事業場 | ||||
| 安全管理者 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | ||||
| 衛生管理者 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | ||||
| 安全衛生推進者 | 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場 | ||||
| 産業医 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | ||||
| 統括安全衛生責任者 | 元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる現場(以下「混在作業現場」という。)であって、これらの労働者の総数が30人以上である元方事業者 | ||||
| 元方安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者 | ||||
| 店社安全衛生管理者 | 混在作業場であって関係請負人の労働者を含め、労働者の総数が20人〜29人である元方事業者 | ||||
| 安全衛生責任者 | 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人 | ||||
| ずい道等救護技術管理者 | 出入口からの距離が、1,000m以上の場所において作業を行うこととなる工事又は深さ50m以上となるたて坑の掘削を伴う工事を行う事業者 | ||||
| ・次に掲げる委員会、組織を設置すること。 | |||||
委員会・組織 |
対象事業場 |
||||
| 安全委員会 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | ||||
| 衛生委員会 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | ||||
| 協議組織の設置及び運営(災害防止協議会) | 混在作業現場の事業所 | ||||
| (安全委員会及び衛生委員会は、安全衛生委員会とすることができる) ・ 安全衛生管理規程を作成し、管理者等及び委員会・組織について職務・役割又は機能を適切に明確化すること。 |
|||||
| [2] 安全衛生教育 | ・ 次に掲げる教育が適切に行われる体制が確保されること。 | ||||
教育の種類 |
対象者又は対象業務 |
||||
| 雇入れ時の教育 | 労働者を雇入れ又は労働者の作業内容を変更したとき | ||||
| 職長等の教育 | 新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者 | ||||
| 特別教育 | (イ) 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 | ||||
| (ロ) アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 | |||||
| (ハ) 特別高圧、高圧又は低圧の充電電路等の取扱いの業務 | |||||
| (ニ) 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務 | |||||
| (ホ) 最大荷重1t未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務 | |||||
| (ヘ) 最大積載量が1t未満の不整地運搬車の運転の業務 | |||||
| (ト) 機体重量3t未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用又は解体用)の運転の業務 | |||||
| (チ) 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務 | |||||
| (リ) 車両系建設機械(締固め用)の運転の業務 | |||||
| (ヌ) コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務 | |||||
| (ル) ボーリングマシンの運転の業務 | |||||
| (ヲ) 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務 | |||||
| (ワ) 動力車で軌条により人又は荷を運搬する用に供されるものの運転の業務 | |||||
| (カ) つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務 | |||||
| (ヨ) つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務 | |||||
| (タ) 建設用リフトの運転の業務 | |||||
| (レ) つり上げ荷重が1t未満のクレーン又は移動式クレーンの玉掛けの業務 | |||||
| (ソ) 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | |||||
| (ツ) ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業に係る業務 | |||||
| (ネ) 特定粉じん作業に係る業務 | |||||
| (ナ) その他 | |||||
| [3] 作業主任者 | ・
次に掲げる作業主任者を選任すべき作業がある場合、作業主任者を選任すること。 (イ) ガス溶接作業主任者 (ロ) コンクリート破砕器作業主任者 (ハ) 地山の掘削作業主任者 (ニ) 土止め支保工作業主任者 (ホ) ずい道等の掘削等作業主任者 (ヘ) ずい道等の覆工作業主任者 (ト) はい作業主任者 (チ) 型わく支保工の組立等作業主任者 (リ) 足場の組立て等作業主任者 (ヌ) 特定化学物質等作業主任者 (ル) 酸素欠乏危険作業主任者(第一種、第二種) (ヲ) 有機溶剤作業主任者 (これらの他にも作業主任者を選任すべき作業がある。) |
||||
| [4] 就業制限 | ・ 次の業務に係る有資格者を有すること。また就業制限に係る業務に労働者を就かせるときには、その資格をチェックすること。 | ||||
業務区分 |
業務に就くことができる者 |
||||
| 発破の場合のせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 | (イ)
発破技士免許を受けた者 (ロ) 火薬類取扱保安責任者免状を有する者 (ハ) その他 |
||||
| つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務 | クレーン運転士免許を受けた者 (イ) クレーン運転士免許を受けた者 (ロ) 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者 |
||||
| このうち、床上で運転し、かつ運転者が荷の移動とともに移動する方式のもの | |||||
| つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務 | 移動式クレーン運転免許 を受けた者 |
||||
| つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務 | (イ)
移動式クレーン運転士免許を受けた者 (ロ) 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
||||
| 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 | (イ)
ガス溶接作業主任者 免許を受けた者 (ロ) ガス溶接技能講習を修了した者 (ハ) その他 |
||||
| 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務 | (イ)
フォークリフト運転技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| 機体重量が3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務 | (イ)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転の技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| 機体重量が3t以上の車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務 | (イ)
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| 機体重量が3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転の業務 | (イ)
車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| 最大荷重が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務 | (イ)
ショベルローダー等運転技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| 最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務 | (イ)
不整地運搬車運転技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務 | (イ)
高所作業車運転技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| つり上げ荷重が1t以上のクレーン又は移動式クレーンの玉掛けの業務 | (イ)
玉掛技能講習を修了した者 (ロ) その他 |
||||
| (これらの他にも就業制限に係る業務がある。) | |||||
| [5] 健康管理 | ・ 次の健康診断について、実施計画を作成すること。 | ||||
健康診断の種類 |
対象業務等 |
||||
| 雇入れ時健康診断(雇入れ時) | |||||
| 特定業務従事者に対する定期健康診断(配置転換の際及び6月以内ごとに1回) | (イ)
さく岩機等によって身体に著しい振動を与える業務 (ロ) 坑内における業務 (ハ) 深夜業を含む業務 (ニ) 粉じん等を飛散する場所の業務 (ホ) その他 |
||||
| 定期健康診断 (1年以内ごとに1回) |
上記(イ)〜(ホ)以外の業務 | ||||
| 特殊健康診断 イ.有機溶剤業務健康診断(雇入れ時、配置転換時及び6月以内ごとに1回) ロ.じん肺健康診断(雇入れ時、配置転換時及びじん肺管理区分に応じ1〜3年以内ごとに1回) |
塗装、防水工事等で有機溶剤含有の塗装等を行う業務 じん肺にかかるおそれがあると認められる作業に係る業務 |
||||
| ハ.その他 | |||||
| [6] 火薬類保安対策 | ・ 火薬類取締役法に定められている以下の事項について基準を定め関係労働者に周知すること。 | ||||
項目 |
保安措置等 |
||||
| 火薬類取扱保安責任者の選任 | (イ)
火薬庫の構造、設備等の監督 (ロ) 保安教育実施状況 (ハ) 定期自主検査の指揮及び監督 (ニ) 帳簿の記載等 |
||||
| 火薬庫の保安 | (イ) 最大貯蔵量 (ロ) 貯蔵上の取扱い (ハ) 盗難防止の措置 (ニ) 火薬庫の構造 |
||||
| 火薬類取扱所、火工所の保安 | (イ) 盗難防止の措置 (ロ) 火薬類取扱所等の構造 (ハ) 帳簿の記載 |
||||
| 保安教育 | 保安教育計画の作成 | ||||
| 定期自主検査 | 定期自主検査計画の作成 | ||||
| [7] 構内外の交通安全対策 | ・
工事用道路及び運行経路を定めること。 ・ 工事現場内の制限速度、合図の統一等交通安全に関する基準を定めること。 ・ 歩行者への安全対象を講じること。 特に坑内の安全通路と車道の区別を明確にすること。 ・ 工事用道路の維持管理を行うこと。 ・ 運転者に対する安全教育を実施すること。 ・ 安全運転管理者を定めること(5台以上)。 ・ マイクロバス等による作業員輸送のための安全管理規程を定めること。 ・ ダンプトラック等への積載重量制限を徹底すること。 |
||||