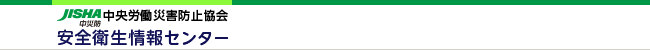安全衛生情報センター
別紙(2)
尿中デルタアミノレブリン酸測定法
浦田グラニツク法(J.Biol chem,Vol 238.PP811.1963) 1 原理 2種類のイオン交換樹脂を用いて、δ−ALAを分離し、ALAピロールをつくり、これをエールリツヒ試 薬によつて赤色に発色させ、比色定量する。 2 器具 カラム (3) 内径9mm前後 長さ30cm 但し、3本のうち1本の長さ10cmのものでよい。 比色計 (1) 552mμ フイルター式の場合はその近くのフイルターを用いる。 その他、試験管、pHメーター又はpH試験紙、三角フラスコ、コガラス棒、ピペツト類、煮沸用湯浴器、 ロート、脱脂綿、純水( )内は1検体当りの本数 3 試薬(後記「参考」参照) ○ 陽イオン交換樹脂 100〜200メツシユ ○ 陰イオン交換樹脂(強塩基性) 200〜400メツシユ ○ メタノール(特) ○ 氷酢酸 ○ 酢酸ソーダ(特) ○ アセチルアセトン ○ 塩酸 ○ 水酸化ナトリウム ○ 塩化第2水銀(特) ○ 過塩素酸(特) ○ パラジメチルアミノベンズアルデヒト(特) 4 試薬の調製 (1) 樹脂の調製 陽イオン交換樹脂について 1検体7ml程度必要 三角フラスコに必要量をとり、純水を10〜20倍量加えて振る、放置、上清をすてる。 以上を上清が清澄になるまで(3〜4回)くり返す。上清を捨て、1N・NaOHを樹脂の10倍量加えて混 合、1晩放置。 上清を捨て、樹脂の10〜20倍量の純水で10回ほど洗滌をくり返すと、pHがアルカリ性でなくなる。 1N・HClで2回洗う。 HClがなくなるまで、水で洗う。約10回 酢酸緩衡液(pH4.8)を入れておく。 (2) 樹脂の調製 陰イオン交換樹脂(強塩基性)について 1検体5ml程度必要 (1)のように、水で洗い、ゴミなど除く。 3N、酢酸ソーダを樹脂の10倍量加え、これで3回洗う。もう1度これを加え、1晩放置アルカリ性で なくなるまで水で洗う。 酢酸ソーダは特級のものでも、クロールイオンclを多量に含むものがあるので事前に硝酸銀でチエ ツクするとよい。 以上の調製法は、パツチ法である。原法はカラムを用いているが、これだと時間がかかる。 (3) 酢酸バツフアー(pH4.6)1M 氷酢酸57ml水を加えて1lにする。 酢酸ソーダ136g水を加えて1lにする。 pH4.8の酢酸バツフアーは、それぞれ、45mlと100gを加え水で1lにする。 (4) エールリツヒ試薬 以下のものを、その都度つくる、5ml/検体必要 パラジメチールアミノベンズアルデヒト 4g 氷酢酸 168ml 過塩素酸 40ml 塩化第2水銀 0.7g 以上の混合物に、水を加えて全量220mlとする。 (5) メタノール酢酸混合物 容量で2:1に混合 (6) 1M酢酸 5 カラムと尿の調製 (1) カラムの調製 第1カラム 調製した陰イオン交換樹脂 第2カラム 調製した陽イオン交換樹脂 第3カラム 調製した陰イオン交換樹脂 1検体につき3本のカラムをスタンドに垂直にたて、綿栓をつめ、水を流す。 駒込ピペツトで、上記樹脂を均一につめていく。 第1.2.3カラム、それぞれ3.7.1cmの高さまでつめる。 つめたら、その上に綿栓をおく。(図)(2) 尿の調製 普通の人の尿で3.0ml、鉛作業者ではALAの排泄量によるが、その1/2〜1/3量を試験管にとり、 pHを5%酢酸で5〜6に調節する。 6 操作 (1) 検体を完全に第1カラムに流し込む。流出液を下で試験管に受ける。 (2) 流下終了後、純水6mlを同一カラムに流し、(1)の試験管に受ける。 (3) (1)と(2)とを併せたもの(流出液)を第2カラムに流し込む。流出液を下で試験管(20〜30ml)に受 ける。 (4) 流下終了後、純水10mlをこのカラムに流し洗う。 洗液は一緒にする。 (5) (4)の流出液に、酢酸バツフア1mlとアセチルアセトン0.5mlを加え、よく混合 (6) 沸澄水溶中に10分間浸し、煮沸する。 (7) 放冷後、第3カラムに流す。流出液はすててよい。 ALAピロールはここに沸縮補捉される。 (8) 1M酢酸5mlをこのカラムに流して洗う。流出液はすてる。 (9) 10ml目盛付試験管をカラムの下に置き、カラムにメタノール酢酸4mlを流し、ALAピロールを流出 せしめる。 (10) 5mlの目盛までメタノール酢酸を加える。 (11) エールリツヒ試薬5.0mlを加え、混合。 (12) 混合後15分で比色 552mμ 7 標準線の作成 原法は、Molar absorbancy 5.3×104として、計算している。 ALAは容易に手に入るので、これを購入して、自ら検量線を作つてもよい。その場合は次のようにす る。 (1) ALA標品 ALA・HCl 分子量 167.6 ALA 分子量 131.1 (ALA塩酸塩結晶100mgがアンプル入りで売り出されている。) (2) 適用量のALA・HClを化学天秤で正確に秤りとり、水を加え、pHを5〜6に調節、更に水を加えて、 ALAとして、10mg/lの標準液をつくる。 (3) これを稀釈して、1.2.3.5mg/lの濃度階段の標準液稀釈系列をつくつて、尿と同様の操作で分 離、比色する。 注:尿ALAの測定には、各種の簡便法が工夫されている。これらの簡便法を用いる場合には本法に 対して比較、較正するこよが必要である。なお、一般には、別添の測定法(Mauzcrall−Granick法) も普及しているので、これによる場合も差し支えないこと。 参考:試薬中の陽イオン交換樹脂及び陰イオン交換樹脂については、浦田グラニシク法の場合、次 のものが用いられている。 陽イオン交換樹脂……アンバーライトIRC50 陰イオン交換樹脂……ダウエツクス1×8 (別紙(2) 別添) 尿中デルタアミノレブリン酸測定法 原理 δ−ALAはアセチルアセトンとの縮合によりピロールを作る。ピロールはエールリツヒ試薬のPジメチル アミノベンツアルデヒドと酸性溶液で赤色化合物を形成する。エールリツヒ試薬による反応に影響を及ぼ す尿中の還元物質はあらかじめカラムにより分離を行う。 試薬および器具(後記「参考」参照) 1 陰イオン交換樹脂 200−400メツシユ 陽イオン交換樹脂 200−400メツシユ 2 4N、2N、1N−塩酸溶液 3 3M、0.5M−酢酸ソーダ溶液 4 1M−酢酸溶液 5 アセチルアセトン 6 酢酸緩衡液(pH4.6) 酢酸ソーダNaCH3CO23H2Oの136gに氷酢酸57mlを加え、蒸留水で1lとする。 7 エールリツヒ試薬 P−ジメチルアミノベンツアルデヒド1gを約30mlの氷酢酸にとかし、過塩素酸HClO4(70%)、8.0ml を加える。その後氷酢酸で50mlとする。この試薬は使用の都度作成する。 8 カラム(内径10mmと8mmの2種類) 9 ウオーターバス 10 分光光電光度計 定量操作法 1 前処理 陰イオン交換樹脂は水洗後3Mの酢酸ソーダ溶液でクロライドフリーになる迄洗い、次に酢酸ソーダが フリーになるまて蒸留水で洗滌する。 陽イオン交換樹脂は水洗後2N−可性ソーダで一夜放置し、蒸留水で中性になる迄洗滌する。 2 定量操作 第1カラム(内径10mm)、第2カラム(内径8mm)のそれぞれの底部に樹脂の流出を防ぐためグラスウール を2〜3mmつめる。 第1カラムには蒸留水に浮かした陰イオン交換樹脂を駒込ピペツトで3ml入れる。 第2カラムには陽イオン交換樹脂を同様に入れ、1.5cmくらいの高さとする。それぞれ蒸留水を通す。 流速は3ml/10minとする。第2カラムには4N−塩酸1ml 1回、2N−塩酸5ml 1回、1N−塩酸5ml 1回 を通す。蒸留水で中性になるまで洗滌する。 1) 第1カラムに尿1mlをホールピペツトで加え、次に蒸留水を2mlずつ5回加える。 2) 滴下液約11mlを第2カラムに加える。蒸留水で洗滌する。この滴下液はすてる。 3) 0.5M酢酸ソーダ溶液2mlずつ4回加え、この滴下液は試験管にとる。 4) アセチルアセトン0.2mlを加え、pH4.6の酢酸緩衡液で10mlとする。 5) 100°Cの水溶中で10分間加熱。 6) 放冷後この溶液2mlをとり、エールリツヒ試薬2mlを加え、15分後に553mμで比色する。 3 カラムの再生 第1カラムに1M−酢酸2ml、0.2M−酢酸2mlで2回洗い、蒸留水で中性になるまで洗滌する。 第2カラムは蒸留水で中性になるまで洗滌する。 計算 吸光度×47=mg/l 参考:試薬中の陰イオン交換樹脂及び陽イオン交換樹脂については、Mauzerall−Granick法の場合次の ものが用いられている。 陰イオン交換樹脂……ダウエツクス2×8 陽イオン交換樹脂……ダウエツクス50×8